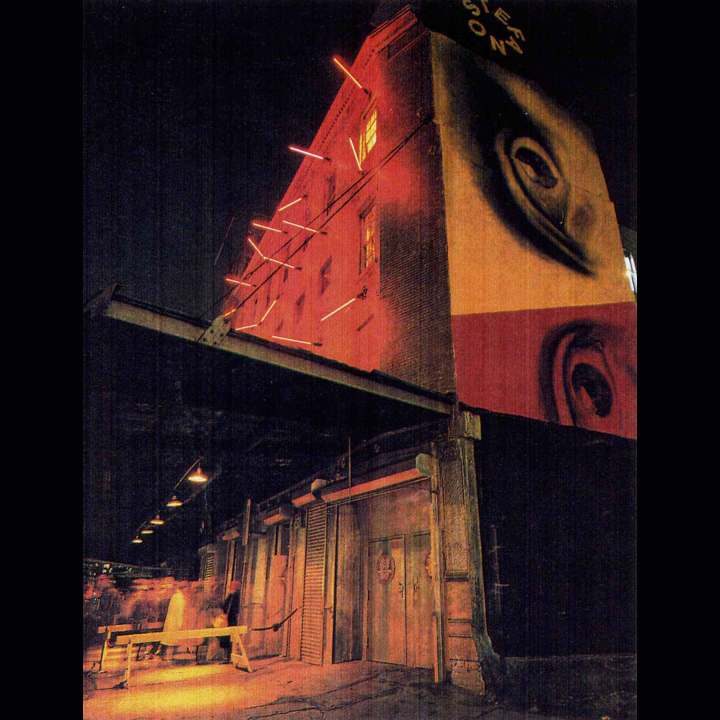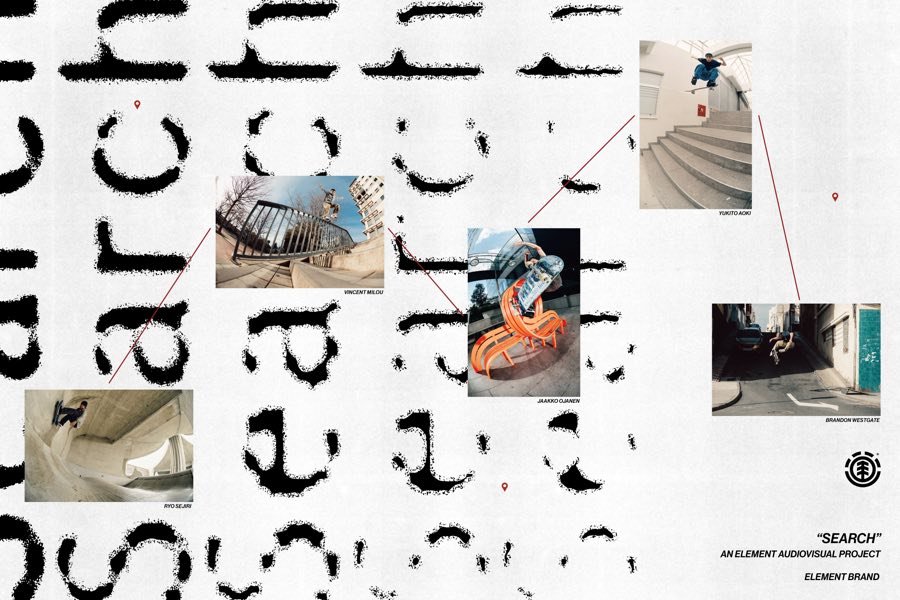CHALLENGERとNEW BALANCE NUMERICによるコラボレーション第3弾の舞台は440。50歳という節目に自身の原点へ立ち返り、"NOISE"と題したパートも完成させた田口 悟。デザインとスケート、ふたつの表現を貫くその姿勢に迫った。
──SATORU TAGUCHI / 田口 悟

[ JAPANESE / ENGLISH ]
Photos courtesy of New Balance Numeric
Special thanks_New Balance Numeric, CHALLENGER
VHSMAG(以下V): CHALLENGERとNew Balance Numericとのコラボレーションも今回で3度目となるけど、過去2回と比べて今回の440で表現したいと思ったことは?
田口 悟(以下T): 普段から履き慣れてて一番滑りやすいと感じるのが440だったから、自然とそのモデルを選んだ感じです。V2にアップデートされたタイミングなのもよかったです。最初のカラーが黒で、2弾目がグレーだったから、グラデーションになるのも面白いんじゃないかと思って今回は白にしました。素材はレザーとメッシュを使うとハイテクな印象になっちゃうから、あえて全部スエードにして昔ながらのスケートシューズっぽいイメージでリクエストしました。当初は「メッシュ部分をすべて変更すると通気性が悪いかも」って指摘されたんですけど、タン部分を目の粗いスポーツメッシュにすることで改善してくれて。通気性が悪いとは感じないです。実際に滑ってみてもアッパーの食いつきがよくて、めちゃくちゃ調子いいですね。
V: New Balance Numericとのコラボ第1弾のときと同じく、アウトソールに骸骨の足のデザインを採用しているよね。
T: シンプルなデザインだったから、どこかにアクセントを入れようって話になって。440でもクリアソールが使えるようだったので骸骨の足を入れました。ただ今回はカップソール形状で以前のものと全然違うから最初のコラボのデザインだと小さくなってしまって、形に合わせて描き直すことになりました。
V: インソールや靴箱の内側にコラージュのアートワークを落とし込んでいるけど、デザインの着想源は?
T: CHALLENGERの14周年のときに作ったステッカーチューンのデザインがあって。どんどんステッカーを貼ってく、スケーター魂で貼ってくイメージで。今回はそこに、地元で個展をしたときに描いた地元モチーフの絵や、New Balance Numericのオフィスがあるロングビーチをイメージしたステッカーの絵を新たに追加して、それをインソールのデザインに落とし込んだっていう感じ。
V: デザイナーとして「スニーカー」というキャンバスに向き合うとき、アパレルやグラフィックと比べて違いを感じる部分はある?
T: どちらかと言えば洋服を作る感覚に近くて、グラフィックというより立体的に「履きやすさ」をイメージしながらデザインしました。実際に旅に行くときもいつも440を履いてて、一番疲れにくい印象があります。New Balance Numericにサポートしてもらってからは一度も足を怪我してないし。やっぱりクッション性がいいですね。
V: では今回のコラボの個人的なハイライトは?
T: CHALLENGERの撮影でLAに行った際に初めてロングビーチのオフィスに行ったんです。それでデザイナーのジェフ(・マイカット)と直接会って話をしました。「ここをこうした方がいい」とかアドバイスをもらいながら、一緒にモノづくりをしている感覚があって。だからこそ自分にとって思い入れのある1足になりました。でもオンラインではすぐに完売しちゃったみたいで、お客さんから「買えない」「もっと数を増やしてほしい」って声が届いて…。またコラボレーションする機会があればもう少し数を増やせたらと思ってます。



V: では今回の「NOISE」パートについて。これは50歳という節目に合わせて制作したパートになるの?
T: そう、50歳の節目。50歳で何か形にしたくて。原点回帰じゃないけど、なんか楽しかったスケートボードを自分なりに表現したというか。
V: では「NOISE」というタイトルに込めた想いは?
T: キース・ハフナゲルと最初にコラボしたときに「どうして僕たちみたいな小さい会社とコラボしてくれたの?」と聞いたんです。そしたら「売上なんて求めていない。ただ“ノイズ”を作って目立つことができればそれでいい」って言ってくれたんです。その言葉がずっと心に残っていて。ノイズって悪いイメージもあったけど…。スケートボードの音だって人によってはノイズに感じるかもしれないし。でも同時に目立つことでもある。そう考えるとノイズという言葉もいいなって。
V: ちなみに今回のパートはいつ頃から撮り始めたの?
T: 2023年の10月末。朝のストリートにこだわりたかったんで、全部朝。
V: 灼熱のこの夏の時期に追い込みをかけて大変だったって聞いたけど。
T: なんかゴールが見えてきてから焦り出して。「いや、これやんなきゃな」と思って、6月ぐらいから本格的に火がついて撮り始めたらもうとにかく暑くて…。その暑さが一番ヤバかったですね。
V: 撮影を通して特に記憶に残っているシーンやトリックは?
T: オープニングにはサプライズで森田(貴宏)くんが登場するんですよ。森田くんとは同じ専門学校出身で、僕が最初に出たビデオもFESN。だからどうしても出てもらいたくて。編集を担当してるクジライくんに相談したら「最初に森田くんに撮ってもらって、オープニングでひと言もらったり、“もっとやれよ”っていう雰囲気を出せたらいいんじゃない?」っていうアイデアが出てきて。それで九五館まで森田くんに会いに行ったら、快く引き受けてくれて。昔からのスケーターは結構上がるんじゃないかなって。
V: 初めて出たビデオがFESNだったんだね。それはイントロでグリッチョしてるやつ?
T: いや、それは『Subway』。その前の1本目の『Far East Skate Network』。専門学校の構内でスケボーを持ってなかったんだけど、たまたまStereoのパーカーを着てたのをきっかけに「お前スケボーやんの?」って声をかけられて。それで一緒に新宿のジャブ池に滑りに行ったら「うまいじゃん」って。さらに「光が丘で大会があるから出てみなよ。オレがジャッジするから」って勧められて出場したら、いきなり優勝できたんです。そこから「じゃあビデオを撮ろう」という流れになって、アキバやジャブ池によく撮影に行くようになりました。
V: 森ちゃんが今回のパートに登場することは、そういう意味でも原点回帰ってことね。
T: そう。もし森田くんに出会ってなかったら、きっとスケボーは続けてなかったと思うし。実家のクリーニング屋を継ぐつもりだったんだけど、無理を言って専門学校に通わせてもらってたから、卒業後は家業を継ぐつもりでした。でも森田くんと出会って、一緒にビデオを撮ったり大会に出るようになって。江口(勲二郎)くんを紹介してもらってMetropiaを作るきっかけにもなったりとか。だからあの出会いがなかったら今の自分はいないと思う。今回のビデオパートはおそらく人生最後になると思うから、そこに森田くんが関わってくれたことは自分にとってすごく大切な思い出になるはずだと思って。
V: なるほど。今の活動の起点だね。では当時のスケートで印象的だったことは?
T: 当時はとにかくNewTypeの存在感がすごくて。アキバにNewTypeが現れると、みんな思わず体育座りみたいなイメージ。そんななかで(館山)憲次郎くんは酒を飲みながらポーカーをやってて。「何なんだこの人は!?」みたいな(笑)。
V: 東京の試写会では森ちゃんと憲次郎をゲストに迎えてトークショーも行ったよね。
T: そう。憲次郎くんとはASANOHAで一緒に働いてたんで。20代の僕を知っている森田くんと30代の僕を知っている憲次郎くんということで。
V: 当時の経験は今の生き方に繋がっていると思う?
T: 自分の人生はすべてスケートボードが起点になってると思うから。グラフィックを始めようと思ったのも、スケートボードの裏に描かれた絵がかっこいいと感じたことがきっかけで絵の学校に通う流れになったし。特に人との繋がりは、ほとんどスケートボードから生まれたものばかりだし。
V: ちなみに新宿とかアキバで滑ってた当時を思い出したり、撮影中に過去と現在が繋がるような瞬間はあった?
T: 森田くんが「じゃあ『Far East Skate Network』で最初に出たスポットに行こうよ」と言ってくれて、そこで撮影しましたね。当時と同じスポットで同じ技をやるっていう。感慨深かった。結局できなかったけど。「ああ、できないんだぁ〜」って(笑)。やっぱり体は全然重くなってます。いや、もう絶対できると思ったんですけどね。やっぱり昔と違いますね、体が。
V: ちなみに一番思い入れのあるカットは?
T: もうハンドレールもやらないし、ステアもやらないし。でかい技で締めるって感じでもないんで、やっぱりオープニングかもしれないです。一番気合入れたから。森田くんにケツ叩かれましたね(笑)。都庁前の飛び出しバンクで最初はガードレールを普通にフラットに置いてたんですよ。そしたら森田くんが「いやこれじゃダメでしょ。もっと上げなきゃ。これ誰もやったことないから」ってめちゃめちゃ高くして(笑)。 それで最初は端っこを飛んでいたんですよ。そしたら「いやいや端じゃダメでしょ。もっと真ん中を飛ばなきゃダメだよ」とか言って。でもちょっとでも低くしようとして、ガードレールを花壇の上に置いていたら「花がかわいそうだ」って。「そんなこと言う人だったっけな、この人?」って思いましたよ(笑)。そのガードレールがめっちゃ高いんですよ。しかもまったく妥協させてくれなくて…。なんとかできたんですけどね。タイミングも全然合わなかったし、最初は絶対に飛べないと思ってたんですけど。
V: でも『Far East Skate Network』に収録された当時のフロントフリップのカットが今回のパートに入っているのもいいよね。当時もよくケツ叩かれてたの?
T: 叩かれてましたね。江口くんは僕よりもっと叩かれてましたけど(笑)。しょぼい技だと使ってくれないし。
V: あのビデオが出たのが1995年だからちょうど30年前の映像だね。
T: たしかにそうだ。当時は20歳(笑)。
V: では今回のパートはデザイナーでありスケーターでもある「今」をどう表現できたと思う?
T: やっぱり原点回帰。昔はスポンサーが欲しくて、すごいことばかりやろうとしてたイメージだけど、スケボーを始めた頃は、ただ乗るのが楽しくて、ビデオを見てワクワクしながら滑るような感じがあって。今回はその感覚に戻ったっていうか、プレッシャーもなく、とにかく楽しんで表現しようっていう。観た人が「スケボーしたくなる」って感じられるビデオになればいいなと思ってます。
V: ピュアな初期衝動だ。
T: でもストリートでのスケートは厳しくなりましたよね。撮影してて昔は警察にしか怒られなかったけど、今回は一般の人に結構怒られたな。ただプッシュしてるだけなのに「危ないから!」って。プッシュしてるだけですよ?
V: そんな環境でも50歳を目前にしてビデオパートを完成させたわけだけど、モチベーションはどこから来てるの?
T: やっぱり目標があった方がモチベーションが上がるし、挑戦したかったんですよね。挑戦が表現なのかな。チャレンジャーなんで。そういうことかな。
V: ということは、撮影を始めた2023年の10月末の段階で50歳までにパートを作ろうって目標があったってわけ?
T: 最初はCHALLENGERでビデオカメラを買ったんですよ。特に目的があったわけでもなく、スケボーを撮るって感じでもなく。それで新しいスタッフがひとり入ったときに、韓国でいいスポットがあったから撮ってもらったら「意外とちゃんと撮れるじゃん」ってなって。それで練習も兼ねて撮影に行くようになって、トリックもどんどん溜まってきて「これはパートにできるな」って思って。それなら50歳で出そうと。でもこれからは50歳のビデオパートが他にも出てくるんじゃないですかね。(米坂)淳之介くんなんて今でもすごいし。
V: 年齢を重ねることでスケートの捉え方に変化はあった?
T: やっぱり一番変わったのは、楽しむようになったことですかね。それでも今回のビデオではなるべくやったことのない技をやろうと思ってチャレンジはしてみたんですけど。難しい技ができたときの達成感はやっぱりすごいじゃないですか。それを味わうためにチャレンジした感じです。あと、やっぱりビデオを回さないとそういうの本気でやらないじゃないですか。カメラを向けられた瞬間は絶対に乗る気になるから、普段はやらないような技にも挑戦できるっていうか。その感覚は若い頃とあまり変わってないかもしれないです。
V: ではCHALLENGERはこれまでいろんなカルチャーと強く結びついてきたけど、今後ブランドとして挑戦してみたい表現は?
T: なんだろうな。洋服屋ではあるけれど、ただの洋服屋ではないっていうか。カルチャーを作りたいんで、なんか面白いことができればいいなっと思ってて。それで今は店内にミシンを置いて、ASAHOHAで一緒に働いてたカバン職人のスケーターを迎え入れてCHALLENGERのオリジナルのバッグを作れるシステムを整えました。そういう面白い試みをどんどんやっていきたいっていうのがあります。また昨年レコード会社も立ち上げて、ボーカルの(長瀬)智也率いるKode Talkersの活動も展開してます。洋服屋でありながら、洋服だけにとどまらないカルチャーを作っていきたいっていう感じです。
V: ではデザインとスケートの両輪で活動を続けるなかで、今の自分にとってCHALLENGERというブランドはどんな意味を持ってるの?
T: 全部、自分にとっては表現ですかね。絵もそうだし、音楽もそう。音楽を聴いて勇気づけられたりワクワクしたりするように、CHALLENGERの洋服も着る人に勇気を与える“勝負服”のような存在にしたいと思ってます。そのためには、やっぱりカルチャーが絶対に必要だと思う。
V: では最後に改めて、田口 悟にとって「スケートボード」とはどんな存在?
T: 表現。スケートボードは人生のすべて。あとスケートボードさえ持ってれば言葉もいらないっていうか。海外でスケートパークに行っても、メイクすれば自然と褒めてくれたりリスペクトがあるっていうか。上手い下手に関係なく仲良くなれる。人と人を繋ぐパイプでもあるし、グラフィックの教科書でもある。すべての原点。スケートボードがなければ自分の人生はつまらないものになってたかもしれない。家業のクリーニング屋を継がなかったっていう心残りはありますけどね。いつかスケートショップとクリーニング屋を組み合わせたら面白いかもしれないですね(笑)。
Satoru Taguchi
@taguchisatoru_
アパレルブランドCHALLENGERのデザイナー。’90年代からスケートシーンで存在感を放ち、デザインとスケートの両輪でカルチャーを牽引してきた。50歳を迎えた今もなお挑戦を続ける。