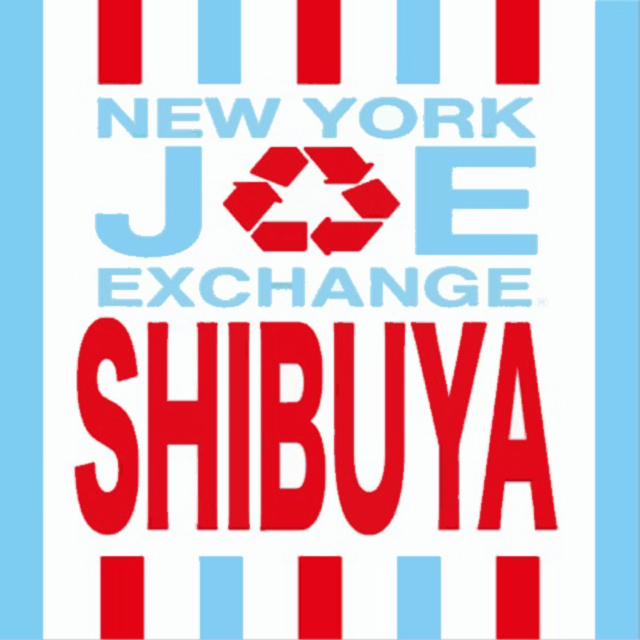‘50年代のフィルムノワールを彷彿とさせる世界観が魅力のボードカンパニー。フィルマーのジョシュ・スチュワートが手掛けるPICTURE SHOWに迫る。
──PICTURE SHOW: JOSH STEWART

[ JAPANESE / ENGLISH ]
Photos courtesy of Picture Show
Special thanks_BP Trading
VHSMAG(以下V): ジョシュはフロリダ出身だよね。スケートとフィルミングを始めたきっかけは? スケートそのものというより、まずスケートビデオに惹かれたそうだね。
ジョシュ・スチュワート(以下J): そう。まず'80年代に兄貴がスケートしてたんだ。よく兄貴の友達のフロリダのプロがうちに泊まりに来てたから、いつもスケーターに囲まれてた。当時はまだ10歳くらいで『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が公開されたばかり。劇中にスケートのシーンがあったからスケートが人気だったんだ。そして家に転がってたスケートビデオを観たら、スケートそのものよりも想像力を掻き立てられたっていうか…何かを感じたんだよね。スケートビデオがカルチャーを上手く表現してたからだと思う。聴いたことのない音楽もたくさん使われてた。'80年代や'90年代にラジオで流れていない音楽を聴くには、まずレコード店に行ってレコードを探さなくちゃならない。オレにとってスケートビデオが異文化への入り口だった。パンクや他のシーンでも同じようなことが起きてたと思う。そうやってキッズたちは新しいカルチャーに夢中になっていったんだ。
V: 最初に観たビデオは何だったの?
J: H-StreetやPowellのビデオだったと思う。でも本当の意味で衝撃を受けたのはAlien Workshopの『Memory Screen』。その頃にはすでにスケートを始めてた。そしてそのビデオを観たときに、本当の意味でスケートビデオの持つパワーを感じたんだ。別世界に連れて行かれたよ。あの作品にはスケート以上の要素がたくさん詰まってる。そんなビデオを作ってみたいと思ったんだ。
V: スケートビデオと同じようビデオカメラも自宅に転がってたの?
J: オレがスケートを始めたのは'88年で、ちょうどハンディカムが一般家庭に広がり始めた頃だったんだ。ちょうど子供の誕生日とかを撮影するために小さなビデオカメラが売れ出した時代。オレの両親も小さなビデオカメラを買ったけど、まったく使ってなかった。それでスケートのセッションに持っていくようになったんだ。
V: そうしてフロリダのローカルビデオやスケートショップのビデオを手掛けるようになったんだよね。『Welcome to Hell』の撮影も手伝ってる。映像を仕事にしたいと思ったのはいつ頃だったの?
J: 当時はインディのビデオプロダクションなんて皆無。大企業のビデオしかなかった。だからスケートビデオで生きていくどころか稼げるなんて思えなかった。でも10代の頃に仲間だけに向けたローカルビデオを作ったんだ。その後、もっと多くの人に観てもらえるような良いものを作りたいと思うようになった。それで16歳か17歳のときに、地元タンパのスケーターたちと一緒にビデオを作り始めたんだ。ちょうどSkatepark of Tampaがオープンしてたからシーンも盛り上がってた。マイク・フレージャーやポール・ジッツァーも毎日のようにバートを滑ってる。そうしてフロリダ州内のいろんな場所に住んでるスケーターがタンパに集まるようになったんだ。最初はみんなと遊び半分で撮影し始めたんだけど、いつからか「ちゃんとしたビデオパートを収録した作品を作りたい」と思うようになった。それで『Prospects』が完成したんだ。誰も観たことないと思うけど、これがオレの初作品。100本作ってフロリダのスケートショップで売ってた感じ。そのときに試写会を開催して、自分の作品を他人が観る姿を初めて目にすることができた。そのときに「これで稼げなくてもいい。最高の気分だ」って思ったのを覚えてるよ。スケートビデオで食っていきたいとは思ってなかったはずだけど、「これをずっと続けたい」とは思ってたね。
V: 『Static』がリリースされたのが2000年。日本でジョシュの名前が広まったのもその頃だったと思う。あのビデオプロジェクトはどのようにして生まれたの?
J: Skatepark of Tampaで初期のTampa AMを観ることができたのが大きかったと思う。今のキッズには'90年代半ばがどんな感じだったかなんて理解できないと思う。1800年代後半のサーカスのようなものだよ。才能を持った人たちが世界中から集まってきて、見たこともないとんでもないトリックを披露するんだ。インターネットなんてない。411VMが始まったばかりで、新しい作品がリリースされるのも数ヵ月に一度。ジェイク・ラップやショーン・マレンドアといったイーストコーストのスケーターを生で見ることができた。スタイルというものを初めて認識した瞬間だったと思う。若い頃はスタイルなんて理解できないものだから。才能あふれるスケーターを目の当たりにして、イーストコースト中のスケーターを紹介する作品を作りたいと思うようになったんだ。
V: ジェイク・ラップやショーン・マレンドアは知り合いだったの?
J: いや、彼らについてはあまり知らなかった。だから他の人も彼らのことを知らないに違いないと思ったんだ。そこで仲間から彼らの電話番号を聞いて「ビデオパートを撮らないか?」って連絡してみたんだ。すると快く引き受けてくれた。そうして『Static』の撮影がスタートした。そしてどんな作品になるのかもわからないまま、まずワシントンDCに行ったんだ。ヤバいスケーターがたくさんいたからワシントンDCのセクションを作りたいと思った。だから撮影の旅を始めていろんな人と出会ったことで、セクションを追加し続ける意欲が湧いてきたんだ。さっきも言ったけど、当時はインターネットもSNSもない。だから他の土地にどんなスケーターがいるかなんて知らなかった。いろんなスケーターと出会う度に「この人たちを誰よりも先に世界に紹介したい」と思ってたね。
V: 『Static II』のボビー・プーリオと『Static IV』のクイム・カルドナのパートは今でも観てるよ。ふたりともまったく違うタイプのスケーターだけど両方とも素晴らしい。彼らとの撮影はどうだったの?
J: 今となっては長い付き合いだよね。あのプロジェクトに取り組んでいた頃は楽しかったよ。プーリオは面白いしスケートも独特で最高。でも同時にクソ野郎でもあるんだ(笑)。ヤツと仕事すると誰でも変な関係性になってしまう。一緒に撮影してると、その半分はケンカしてるような感じ。でもあの作品のために撮ったフッテージどれも最高だった。ヤツは他の誰も持ってない独特の目線でスポットを読んでる。どこで滑ってても面白く見える。ヤツとは完成までに何度も大変なやり取りをしたけど、それが良かったんだと思う。オレはある程度プーリオのセンスの影響を受けてるからね。ヤツのおかげでものの見方が変わったと言っていいと思う。
一方でクイムはまったく違うタイプ。波長が独特だから、オレの目線で見るクイムの姿を見せたいと思ったんだ。撮影のためにヤツを確保すること自体大変だし。約束してもなかなかスポットに現れないし、現れたとしても仲間を何人も連れて来たりする。クイムはニュージャージーに住んでてオレはブルックリンにいるから、「来週のいついつの何時にマンハッタンで会おう」って約束が必要だろ? でも来ないことが多いんだ。やっと会えたと思っても、1日中ドライブして女の子に声をかけたり、オレをレストランに連れて行ったり、レコーディングスタジオに立ち寄ったり…。クイムに何かを求めるということは、1日中釣りをしながら魚がかかるのを待つようなもの。でもそれが実現したときには報われる。あんなヤツは他にいない。ゴンズみたいだよね。最高のスタイルの持ち主だし。クイムが実際に現れてクリップが撮れる度にラッキーだと思ってた。それにポジティブで面白いから一緒にいて楽しいんだ。ヤツは純粋でRAWなストリートスケートのエッセンスを誰よりも体現していると思う。
V: 最高のビデオパートだよね。ところでフロリダからNYに移ったのはいつ?
J: NYに移ったのは『Static III』に取り組むため。だから2006年だね。撮影のために2、3ヵ月だけ滞在するつもりだったんだけど、初日に「ここに住みたい」と思ったんだ。
V: Theories of Atlantisは? ディストリビューターの前はウェブサイトだったよね?
J: 『Static II』を作ったときにビデオのプロモーション用にウェブサイトを作ったんだ。『Static III』でもウェブサイトを作ったんだけど、ビデオが完成する度にウェブサイトを作るのはバカげてると思ってね。そこでブログを書いたりインタビューを掲載できるプラットフォームを作ることにしたんだ。そして他の人の作品も買えるようにして、世界中のインディビデオのハブにしたいと思った。それから数年後にソイ・パンデイとヴィヴィアン・フェイルがMagentaを立ち上げて、オンラインストアでデッキを取り扱ってくれないかと頼まれた。Theories of Atlantisがディストリビューターになったのはそれがきっかけ。2000年代半ばから後半にかけてはBakerやGirlのような大きなカンパニーしかなかった。スモールブランドがやっていくには大変な時代だった。だからイーストコーストのいろんなスモールブランドで団結していろいろやっていきたいと思ったんだ。そして仲間のポール・シャイアがIsleを始めてそれを取り扱ったりしながら成長してきた感じだね。そうやって今の形になったんだ。
V: スケーターが運営するブランドが手掛けるスケートビデオの魅力は?
J: 毎年、その年のお気に入りのビデオ10本を紹介する記事を書くようにしてるんだ。そしていつもランクインするのがインディビデオ。インディビデオの制作者は正しい理由で作品を作ってると思うんだ。ただ金を稼ぐことが目的のスモールブランドも確かにある。でも昨年は…クロアチアのビデオは観た?
V: 『Finta』のこと?
J: そうそう。あの類のビデオはクリップを少し観ただけでは良さが伝わらない。機材もしょぼいカメラでフィルミングもイマイチだし。でも個人的に2020年で一番面白いビデオだったんだ。心がこもってて、楽しくて、スケートもいい感じ。ノーマークの国のシーンを観ることができたし。こういうビデオには興奮するね。地元フロリダでは何年も前からいろんなことをやってたけど、カリフォルニアがずっとスケートシーンの中心だったから誰も注目してくれなかった。だからアンダードッグを応援したいんだ。
基本的にインディブランドのオーナーは自分でビデオを撮ったり、グラフィックを作ったり、営業をしたり、自腹で運営している。すべてを自分でコントロールできるし、お金のためだけにやってるわけじゃない。さっきクイムやプーリオのパートが好きだと言ってくれたけど、それはスケートのスポーツやビジネスの側面ではなく、そのアート性を重視しているからだと思う。スモールブランドはスケートのアートの部分を大切にしている。一方で一部の大企業は金儲けのためにスケートカルチャーを利用している。スモールブランドはコミュニティのなかでカルチャーを維持することに長けていると思う。オリンピックでスケートに注目が集まり人気になることでカルチャーが失われる可能性は十分にあり得る。でもアンダーグラウンドのシーンはつねに存在し続けるし、そうやってカルチャーも守られていくんだと思う。
V: そういったスケーターが運営するスモールブランドのディストリビューションをずっと続けてきて、自分でもデッキブランドを立ち上げたよね。Picture Showはどのようスタートしたの?
J: ディストリビューションやすべての活動を集約するTheoriesというブランドはすでにあったけどね。これまでTheoriesのチームに参加していろんなプロジェクトに協力してくれる仲間もいたけど、デッキブランドに所属してるわけじゃなかった。だから最終的には彼らが所属できるデッキブランドが必要だったんだ。素晴らしいアーティストも周りにいたし。彼らのアートワークはTheoriesで使ってたけど、どれも深みのあるものばかりだった。だからその世界観をベースにしてイケてるブランドを構築できると思ったんだ。スケートビデオと似てるよね。アイデアは単なるテーマに留まることなく、映像で表現したいフィーリングとして世界に発信することができる。そしてその感覚を伝えるために、然るべきフッテージ、音楽やスキットのアイデアに没頭する。オレらにとってPicture Showはひとつのスケートビデオのようなものなんだ。「これを作りたかったんだ!」と思えるものだね。
V: Picture Showには独特のヴァイブスがあるよね。
J: すべてはブライス・マンデルという仲間から始まったんだ。カリフォルニア出身のスケーターで、’50年代のハリウッドをモチーフにしたドローイングをたくさん描いてる。フィルムノワールみたいな感じ。かつてAlien Workshopのビデオがそうしたように、ブライスのアートワークと個性がオレの想像力を掻き立てたんだ。また’80年代のアナログなもの、例えば奇妙な広告やその雰囲気とか、自分たちが素晴らしいと思うものをヤツのアートと結びつけてる。子供の頃に『Boy’s Life』っていう雑誌があったんだ。キャンプとかの雑誌なんだけど、巻末にX線透視ゴーグルやシーモンキーなどのおかしな広告が掲載されてて、オーダーすると想像とまったく違う代物が送られてくる(笑)。今はもう存在しない奇妙なもの。何が届くかわからない、実際の品物よりも期待しながら待ってる時間のほうが楽しい…そういう感覚。フィルムの撮影も同じだよね。お金がかかるし、重いし、扱いも大変だし、現像してみないとどんな感じになってるかわからない。そのプロセスが楽しいんだ。そういったことがPicture Showのグラフィックのコンセプトやアイデアを生み出してる。さらにジョシュ・コーラスというアーティストにも出会ったんだけど、ヤツはブライスの作品とはまったく違うデジタルアートを手掛けてる。でも不気味な感じがよく似てるんだ。まるでパラレルワールドのような感覚。このふたりは相性がいいね。
V: ジョシュは20年以上も前からスケートビデオを作ってるよね。Picture Showの映像作品の方向性も自分で決めてるの?
J: Picture Showに関しては別のフィルマーにビデオを作ってもらうのがいいと思ってる。オレのスタイルとは違う感にしたいから。ただ他の人に任せるのは怖くてなかなかそうできないんだけどね。最初の2、3本は自分で作りたいと思ってる。今回の新作はPicture Showの世界に入り込めるようなものにしたかった。主にテイラー・ナロッキーと一緒に作ったんだけど、ヤツの初プロデッキが出るんだ。だから最後にヤツのフルパートが収録されてる。ここ2、3年、ずっと一緒に撮影をしてるんだ。地下室で昔の名作映画のシーンを自分たちのスタイルでリメイクするような撮影をしてきた。最初にチームモンタージュも入ってる。フィルムノワールのような、’50年代のクラシックなショットのような雰囲気。でも凝りすぎたスケートビデオも考えものだね。スケートだけを観たいスケーターが多いから…。バランスが難しいよね。

V: ひたむきさが伝わってくるね。スケートビデオに求めるものは?
J: ただのスケートと音楽だけの作品は好きじゃない。最近はみんなスケートが上手いから…。それよりもスケートの新しい見方ができる作品を観たいね。たとえスケートが最上級じゃなくても周りと違ったユニークなものであればいい。もしフルレングスを作るとしたら、これまでにない新しいことやフィーリングを改めて生み出すのは大変だろうね。だから時間がかかってしまうんだ。別のプロジェクトにも取り組んでるんだけど5年もかかってる。何かを完成させるのは大変なんだ。だから撮影を始めて、完成させて、確実に世に出すことができるショートエディットはいいよね。でも最悪なのは、人が楽しんで観てる姿を見ることができないこと。スケートビデオを作る一番の楽しみはそれだから。試写会でみんなの反応を見たり、出演したスケーターが賞賛や拍手を受けるのを見ることができる。オンラインの場合は、みんな自分の部屋で小さな画面で観るだけ。せっかくの体験が台無しだ。
V: ひとつのクリップを撮るのに、何時間、あるいは何日もかかることがあるよね。モチベーションをキープする秘訣は?
J: そうだね(笑)。2、3日撮影してもクリップが撮れないこともあるし…。フロリダ時代は車があったから楽にスポットまで移動することができた。でもニューヨークに住んでるこの15年間は車なんてない。すべての機材を自分で背負わなきゃならないんだ。平日は1日中オフィスで仕事をして土曜日に撮影に出かける。16mm、VX、スチールカメラ…すべて背負っていくんだ。マジで大変だけど…たとえクリップが撮れなくても1日の終わりには最高の気分。本当にがんばったという気持ちになれる。モチベーションに関しては、仲間と一緒に仕事をしているから。ジャマール・ウィリアムスやスティーブ・ブランディは家族のような存在だし。オレは酒を飲まないからバーにも行かない。撮影が仲間との時間。そして編集作業をしているときにいい感じの曲を見つけてそれをスケートクリップに合わせたら上手くいったり、16mmの映像が完璧にハマったりしたときにすべてが報われたように感じる。映像制作のプロセスは苦労の連続だけど、すべてのピースが揃ったときに25年前に初めて経験したときのような気持ちになることができる。オレはその感覚を追い続けてるんだと思う。
V: スケートコミュニティの枠を飛び出して映画を作りたいと考えたことはないの?
J: 以前はよく考えてたけどね。いつかそうするかもしれないけど…まだわからない。でも今もこの仕事が好きなんだ。これまで5本のスケートビデオを作ったけど、毎回「これが最後」って誓ってた。25、6歳で引退するフィルマーもたくさんいるし。いつも終わりにしようと思っても、撮ったことのないスケーターと一緒に撮影することになったり…。何かのきっかけでまた火がついたりするんだ。「よし、もう1本だけ」ってね。
V: ではPicture Showの展望は?
J: まだPicture Showのフィーリングを形成してるところだから。伝えたい世界観を構築してるところ。まずはチームを知ってもらってオレらが作り出そうとしている感覚をみんなに伝えたいと思ってる。アーティストや画家は、自分の作品を人に体験してもらいたいと思うもの。それと同じで、スケーターやアーティストと協力しながら新しい世界観を構築し、それをみんなに体験してもらうと同時に評価してもらいたいと思ってる。自然の流れで然るべきチームとアーティストが揃った。これからもそうやって成長していければと思ってる。どんなブランドでも最初の2、3年の間に本当の意味で花開いて新しい世界を提示するもの。Picture Showもそうできることを願ってる。楽しいプロジェクトを形にして最高の体験を提供していきたいと思ってるよ。





Josh Stewart
@mystaticlife
@pictureshowstudios
フロリダ州出身。『Static』シリーズで知られる’90年代から活動するフィルマー兼アングラ系スモールブランドの伝道師。ディストリビューションTheories of AltantisとともにPicture Showを運営。