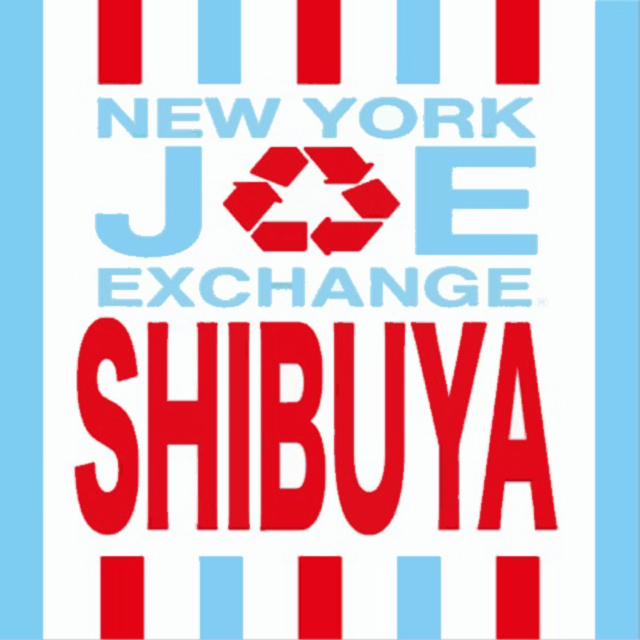カナダ・モントリオール発のスケートカンパニーSTUDIO。ファウンダーのジャイ・ボールの歴史を辿りながら、クリーンで洗練された同ブランドの軌跡を紐解く。
──JAI BALL

[ JAPANESE / ENGLISH ]
Photos_Jacee Juhasz
Special thanks_Yuji Kawamoto
VHSMAG(以下V): まずは基本的なことから。カナダのモントリオール出身なんだよね?
ジャイ・ボール(以下J): そうだね。生まれも育ちもモントリオール。25歳までずっとモントリオールで、26歳の頃にバンクーバーに移った。妻のローラと出会ってから16年間、両都市を行き来しながら生活してる。
V: じゃあモントリオールでスケートを始めたんだね。
J: そう。10か11歳の頃にモントリオールでスケートを始めた。今41歳だから、'90か'91年くらいかな。Bones Brigadeの人気が終わった後でニュースクールの波が起きてた頃。かなりエキサイティングな時代だった。
V: 当時影響を受けたものは?
J: ThrasherやPlan B、World Industries、101のビデオとかを観てたけど、地元のモントリオールにもいいシーンがあった。だからカリフォルニアとローカルシーンの両方。モントリオールのダウンタウンでスケートし始めたのは'92年か'93年頃なんだけど、エリック・メルシエ、フィル・ボーセジュール、フランク・セントピエール、リックやキットとか年上のイケてるスケーターがたくさんいた。オレらにとってはモントリオール市役所がEMBのような存在だったんだ。みんなPLG(ピエール・リュック・ギャニオン)やマックス・デュフォーといったバートスケーターとも仲良かった。PLGの父親が郊外でインドアパークを運営していたから、冬になるとそこで滑ってたし。季節に関係なく1年中滑ることができたから強いシーンが築かれたんだと思う。
V: ジャイは元々Zoo Yorkのライダーだったんだよね?
J: そうだね。初めてのスポンサーはローカルショップだったけど、それ以外だと'99年にカナダのスケートプログラムを始めたDC。当時はカナダチームなんてなかったからうれしかったのを覚えてる。'90年代はショップスポンサーくらいしかなかったから。ボードスポンサーがついてるヤツなんていなかったし、誰もカリフォルニアに行ったことすらなかった。そこでディストリビューターができてカナダのプログラムが始まったんだ。まずはDCカナダに加入して、次にZoo Yorkカナダ。それから間もなくしてパートナーのダレル・スミスと一緒にStudioをスタートしたんだ。彼は亡くなってしまったけどね。
V: Studioが始まったのは2008年?
J: StudioはもともとTシャツ会社として2006年にスタートしたんだ。それでダレルと「ボードブランドにしよう」って感じになった。それがモントリオールで形になったのが2008年だね。
V: 当時は他にもドメスブランドはあったの?
J: あったね。当時はマックス・デュフォーのPremiumがあった。ウッドショップ兼ブランドなんだ。その他にも小さなブランドがいくつかあったけど、オレらが好きなスケートを反映させたようなものはなかった。
V: 自分のブランドを始めてみてどうだった?
J: 最初は手探りだったよ。本当に小さなブランドだったから。ふたりとも他の仕事をしながらビデオ制作を始めて、最低でも年に2本は作るようにしていた。取り引きはスケートをしながら知り合ったカナダのショップから始めて、そこから徐々に成長していった。でもビジネスはなかなか大きくならない。そうして2011年頃にダレルが他の仕事をするためにトロントに戻ってしまったんだ。でもオレは諦めたくなかった。状況が好転したのは2012年の春にデビュービデオ『Mood Lighting』をリリースした頃。でも2017年にトロントでダレルが車に轢かれて亡くなってしまった。だから本当に…ダレルの冥福を祈ってるよ。ヤツがきっかけでStudioが生まれたんだから。ヤツはスーパー8や16ミリに傾倒してた。昔からアーティスト気質だったんだ。Studioのビジュアルの方向性を決定づけたのもヤツだった。ダレル・スミスなくしてStudioはない。
V: Studioというブランドネームの由来は?
J: ブランドネームを考えたのもダレル。ヤツはオンタリオ州のロンドンで仲間とTシャツのスクリーンプリントをしてて小さなスタジオを持ってた。Studioというブランドネームもそこで生まれたんだ。
V: Studioのビジュアルはクリーンで洗練されてるよね。センス的にどんなものに影響を受けているの?
J: 自分の人生すべてが集約されてると思う。高校卒業後に2年ほどクリエイティブアートの大学に通ってたんだけど、祖父がアートディレクターであり画家だったんだ。祖父は'50年代から'70年代にかけて雑誌のアートディレクターをしてた。昔ながらの切り貼りのレイアウトをしてて、それを近くで見ながら育ったんだ。そうやって自分のテイストが育まれたんだと思う。年を重ねるごとに自分の好きなものが決まってきて、それを参考にして仕事に反映させてきた感じかな。ポール・ランドやソール・バスといった'40年代、'50年代、'60年代に活躍したグラフィックデザイナーを知ってからは、時代を超越したデザインスタイルに感動するようになった。あとは子供の絵本や古い店の看板とかを見て何となくインスピレーションが湧くこともある。妻のローラも素晴らしいセンスの持ち主で、いつもいいアイデアを与えてくれる。だからまずインスピレーションを得て、そこからデザインの作業に移る。'90年代に育ったから昔のWorld Industries、GirlやChocolateにも多大な影響を受けてる。だからいろんなものが混ざってる感じだね。
V: ちなみに両親がビートニクだったんだよね?
J: どちらかと言えばヒッピーなのかな。母方の祖父母がビートニクだったんだ。祖父はイギリスのリーズ出身で、祖母はカナダのニューファンドランド出身の100%レバノン人。'40年代に出会ったんだ。祖父は『MAD MEN』に出てくるような人だった。クリエイティブで頭が良く、1日中酒を飲んでタバコを吸い、誰も吸っていない時代にウィードを吸い、'50年代にはゲイ雑誌を発行していた。当時はゲイ雑誌を作るなんてかなり際どいことだったからね。そうやって彼らは自分たちの子供を自由で創造的に育てたんだ。芸術にも傾倒してた。母が歌手や声優になったのも彼らの影響が大きいと思う。だから家族はみんな芸術を大切にしてて、オレにやりたいことがあれば何でもサポートしてくれたよ。
V: 先進的な考えを持った家族なんだね。
J: 両親はふたりとも映画や音楽が大好きで、オレもそれに囲まれて育った。学校でも映画をテーマにしたクリエイティブアートのクラスでがんばったし。10代後半の頃はとにかく映画を作りたいと思ってたのを覚えてるよ。'60年代や'70年代の映画に夢中になって、それが今のスケートのビデオ制作に繋がったんだと思う。
V: カナダを拠点にブランドを運営するのは大変だと思う?
J: 今はそれほど大変じゃないと思う。まあ、1年の半分は雪が降るから簡単じゃないけどね(笑)。最初の一歩を踏み出すのが一番大変だったかな。特に'90年代初めのオレらの世代はスケートの中心地がとても遠い場所に感じられた。'90年代初め当時はモントリオールからカリフォルニアに滑りに行くスケーターなんてほとんどいなかった。仲間のフィルとエリックが'94年か'95年にSFに行くまで皆無。ヤツらからEMBの土産話を聞くのが楽しかったのを覚えてるよ。そしてダレル・スミスが'02年か'03年にSFに行ってWestern Editionに加入したんだ。Pier 7でヤバいフッテージを量産してフックアップされたんだよ。だからダレルのおかげで「SFに行ってみたい」と思うようになったんだ。それで'04年か'05年に初めてSFに行ったんだけど、当時はそれが大きな出来事だった。旅をして人に会えば会うほど、カナダで何かできるんじゃないかと思うようになったんだ。今やスケートは完全に国際化していて、素晴らしいブランドがそれぞれの国やシーンをアピールしてる。まあ、オレらはまだ小さいブランドだから大変なことも多いけどね。
V: インターネットの普及で世界は狭くなったよね。
J: そうだね。今はあまり距離を感じない。Studioを初めてもうすぐ12年になるけど、時間の経過とともにゆっくり成長してる感じかな。'15年までは流通がほぼカナダに限定されてたし。とにかくビデオを作り続けて新しい人と出会ってきた。ゆっくりと、着実に成長してるね。
V: Studioを運営する上で譲れないことは?
J: 自分が信じる美学や価値観。最初の頃はダレルもオレもアイデアがたくさんあって、とにかくいろんなことを試してた。型にハマることなくオーガニックな形で進めるのが大切だよね。でも結局のところ、自分の好きなことをやってそれがうまくいくことを祈るしかないと思うんだ。じゃないと自分が何をしてるのかわからなくなるから。何事もビジョンを持ってなければ難しい。行きたい方向があるなら、それを100%受け入れて突き進むしかない。そうすれば最高の仕事ができると思う。そして自分のやってることを気に入ってくれるニッチな人たちを見つけることができるんだと思う。
V: ライダーは全員カナダ人なの?
J: '15年のシカゴツアーで出会ったブレット・ワインスタインというアメリカ人ひとりを除いて全員がカナダ人かな。そして最近、フランス・ボルドーからアンドレア・デュプレがチームに参加してる。初めてのヨーロッパ人ライダーだね。つまり10人のうち8人がカナダ人ということ。
V: カナダ発のブランドということで、カナダ人としてのプライドのようなものはあるの?
J: 面白いことに、Studioがスタートした頃はカナダのスケートにはあるイメージがあったんだ。ホッケー、ビール、木こり、コンクリートパークといったイメージ。でも当時のオレらはまったく違った。だからカナダ人としてのプライドというよりは、自分たちのクルーや自分たちのやってることに誇りを持ってたのかもしれない。'90年代終わりから'00年代初めにかけて、オレらは小さなビデオプロダクションをやっていて、モントリオール初の大規模なビデオプロジェクトを形にしたんだ。まだVHS形式の時代だよ。だからモントリオールのシーンを発信したいという意識があったんだ。そして昔からNY、フィラデルフィア、SFのシーンが好きだった。だから自分たちの街からもアーバンスケーティングを発信したかった。そういう意味では自分の街に誇りを持ってると言える。というのも当時のカナダでは街の雰囲気を活かしたスケートが見過ごされていた。みんなZeroみたいなハンマー系ばかり。オレらはモントリオールのダウンタウンのシーンを表現したかったんだ。
V: 今はブランドが多くてマーケットは飽和状態だよね。Studioの強みは?
J: 意識して目立とうとするのは難しい。ポール・ランドはかつてこう言ってた。「独創的であろうとするな、ただ優れていればいい」って。それに意図的に人と違うことをするのは難しい。だからリアルなビジョンが必要だと思う。自分のやってることが人が夢中になれるようなリアルなものであり、独自の声を持ってることを願うしかないんだ。
V: 過去のコレクションでは料理のレシピ本とかエプロンを出してたよね。あれは新鮮だった。
J: ありがとう。Studioでちょっとした雑誌のような印刷物を作ってて、それにブレットのインタビューを載せたんだ。「ロックダウン中は何をしてた?」という質問の回答が「料理」だった。オレも料理が好きでゴードン・ラムゼイの料理番組とかを観てたんだ。それでレシピ本を作ることにしたんだ。でもブレットにはギリギリまで何も言わなかったから申し訳ない気持ちでいっぱいだった。とりあえずデッキ、エプロン、雑誌を作って、プレオーダーを取ってから「よし、レシピ本をまとめてくれ」って伝えたんだ。ブレットもそのアイデアを気に入ってくれて協力してくれたから安心したけど(笑)。
V: ルックブックやインタビューを収録した雑誌みたいなものも作ってるんだね。
J: そう。実はStudioをやりながらダレルと一緒にプリントショップで働いてたことがあったんだ。大学に併設されたConcordia Copiesっていうイケてるプリントショップ。そこでグラフィックデザインや印刷の仕方をたくさん学ぶことができた。オレは雑誌を読んで育った。15年くらいの間、カナダにはスケート誌が4つくらいあってどれも健全だった。今でも2誌が残ってるけど、年に2回くらいしか発行されてない。とにかく才能のあるフォトグラファーがいるのに、写真の使い道がないっていう状況が続いてたんだ。だからその写真で何かを作りたいと思った。ルックブックじゃなくて、もっと雑誌らしいものにしたかったんだ。
V: なるほど。雑誌作りは大変だからすごいなと思って。
J: でもこの雑誌を作るきっかけはスケートそのものじゃなかったんだ。レストランで待ってたら、エルメスのイケてる雑誌がたくさん置いてあってそれを見てたんだよ。編集も素晴らしくて記事もクールだった。自分で作れば文句を言われることなく好きな内容にできる。まあ、楽しいけど実際作るのは大変だよね。お金がかかるから数百部しか作れないし。でもこれからは部数を増やしてより多くの人に見てもらえるようにしたいね。
V: スケーターが運営するブランドの魅力は?
J: というか、スケートブランドを運営するにはそれしかないと思うんだ。ステイシー・ペラルタ、エド・テンプルトン、リック・ハワード、マイク・キャロル、ディル&AVE…これまでいろんなスケーターがブランドを運営してきた。Studioを始めた頃のオレはすでに28歳。「クソッ、オレは年寄りだ」って思ったのを覚えてるよ。だってリック・ハワードとマイク・キャロルがGirlを始めたときは20歳と22歳だったから。ふたりともずっとリスペクトしてるスケーターだよ。スケーターとしてある程度ストリートという現場にいないと、時代に取り残されてしまうと思う。
V: Studioを続ける原動力は?
J: オレの場合は外に出てスケートしたり、仲間と一緒にクールなプロジェクトに取り組んだりすること。どうせ働かなくちゃならないんだから、好きなことを仕事にしたほうがいいだろ? 家族、ローラ、息子のローリー、みんなで楽しめるものを作ること。いまだに新しいトリックを覚えたいと思うし、自分のクリップの撮影にもこだわってる。41歳になった今でも次のビデオのことを夢見てる。いろんな意味ででまだ子供なんだ。でもそこが一番好きなところだね。スケーターはみんなピーターパン症候群だよ。ひたすらやりたいことを追い求めてる。
V: いいね。では今後の活動予定は?
J: 映像がたまってるからそれをどうするか考えてる。一時期は毎年大きなビデオプロジェクトを形にしてたけど、これからミニビデオで刻む感じになるかな。みんな学校に行ったり仕事をしたりしてるからね。これがスモールブランドの現実だよ。ライダーのほとんどが仕事をしながらスケートしてる。みんなで一緒に戦ってるんだ。みんなそうやってビデオパートを出そうとしてるから、ひとつひとつ形にしていきたいね。
V: では最後に、Studioのゴールは?
J: オレはずっとこれだけで生計を立てたいと思い続けてきた。正直なところ、そんなこと無理だと思ってたけどそれが現実になった。その先どうしたいかって? 今のスケートシーンはマジでクレイジーだ。いろんなことが同時多発的に起きてる。成長しながらいかに誠実さを維持するか。だから本当にやりたいと思えることをやりながら成長して、Studioのイメージをキープしたい。そしてライダー、フィルマーやサポーターがもっとお金を稼げるようにしたい。オレはみんなに多くを与えてもらってるわけだから。ライダーが安定した給料を得て、ワクワクしながら仕事ができて、ヤツらの生活を良くできるような本格的なブランドにしたいと思ってる。それがオレの願いかな。みんなの人生がこれで良くなることを望んでるよ。

Jai Ball
@jai_ball
@studioskateboards
カナダ・モントリオール出身。スポンサードスケーターとして活動した後、2008年にアーバンスケートを体現するブランドStudioをスタート。現在はモントリオールとバンクーバーを拠点にさまざまなプロジェクトを手掛けている。