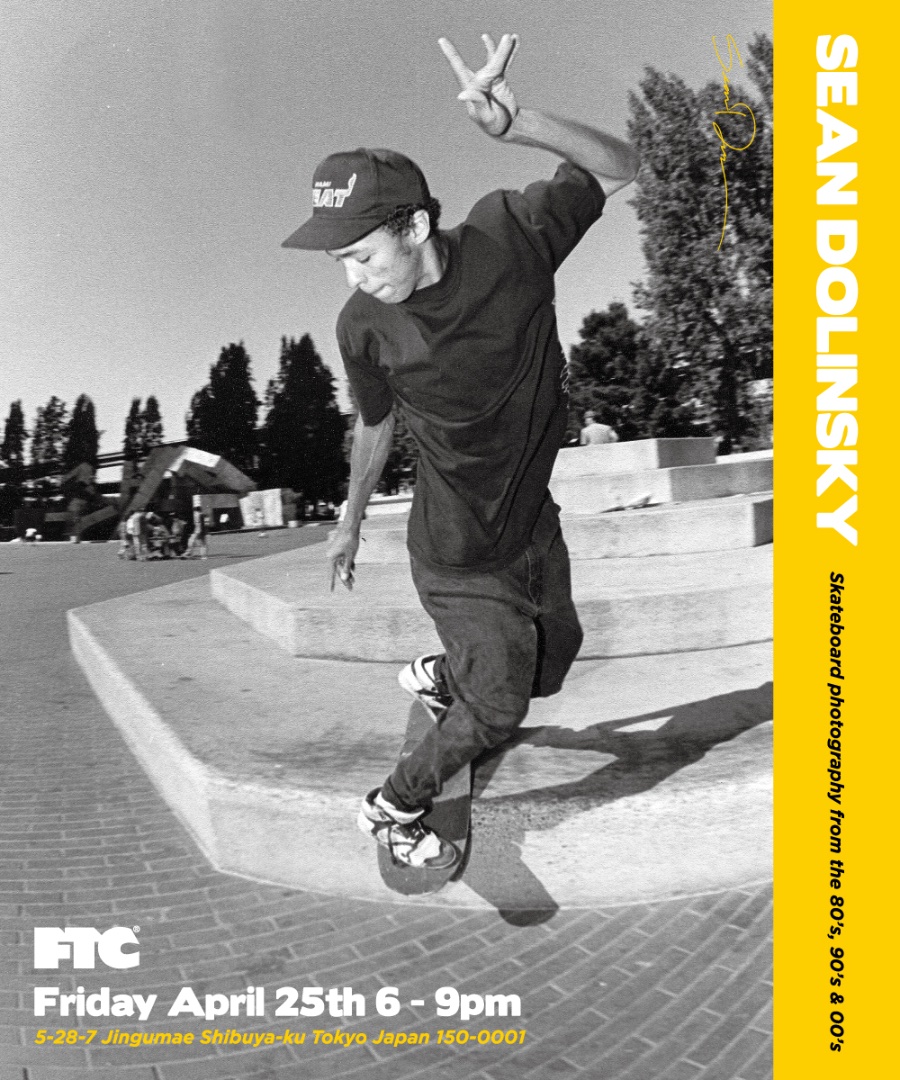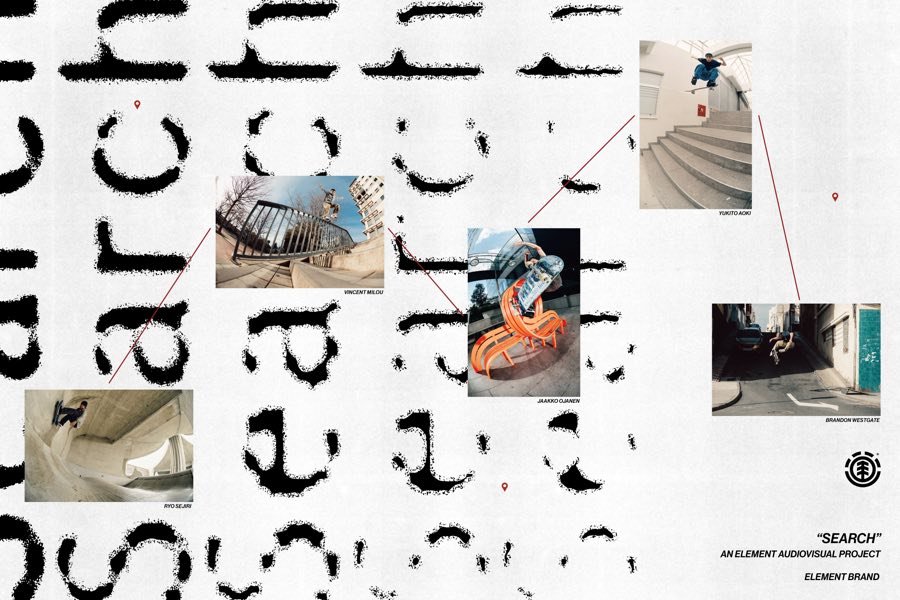'80年代後期のPOWELL PERALTAから'90年代のWORLD INDUSTRIESのアナーキズムの台頭まで、スケート史の劇的な変革期の中心に立ち続けてきたアーティスト。VCJの後を継ぎ、スティーブ・ロッコのカオスの世界を経験し、現在はSTRANGELOVEを通してスケートアートの在り方を問い直し続けている。キャリア初期、'90年代の狂騒、そして現在のボードグラフィックについて。HESHDAWGSの20周年を記念した個展のために来日したタイミングで話を聞くことができた。
──SEAN CLIVER / ショーン・クライヴァー

[ JAPANESE / ENGLISH ]
Photos courtesy of Sean Cliver
Special thanks_Heshdawgs
VHSMAG (以下V): スケートボードに初めて触れたのはいつ? 最初にその世界へ惹かれたきっかけは?
ショーン・クライヴァー(以下S): 1986年の夏だった。親友が兄の影響でパンクロックにハマって、ディスカウントストアで安い台湾製のコンプリートデッキを買ったんだ。楽しそうだったから自分も同じ店で似たようなものを買ったんだけど…その後、初めて手にした Thrasher で自分のデッキがどれだけ恥ずかしい代物だったか思い知らされた。親友はすぐにパンクにのめり込んでバンドを始めるためにスケートをやめてしまった。でも自分は完全に夢中になった。特に地元ウィスコンシンの小さな町にプロクオリティのスケートボードを扱うバイクショップがあると知って、漫画のコレクションを売り払って初めて本物のデッキ、Powell Peraltaのマイク・マクギル “Skull & Snake” モデルを手に入れてからは、毎日スケートしてオーリーを覚えることが人生の使命になったんだ。
V: スケートインダストリーで働く前はどんなアートやグラフィックが好きだった?
S: 自分はずっと漫画家になりたいと思って育ったんだ。15歳のときには25セントで郵送販売していたミニコミまで作っていた。でも初めてスケートショップに足を踏み入れて、壁一面のボードグラフィックを目にした瞬間、「自分がやりたいのはこれだ」と確信した。そもそも漫画家としては大して上手くなかったけれど、スケートボードの裏側に絵を描くことなら自分にもできるかもしれないと感じたんだ。特に衝撃を受けたのは、Powell Peralta、Santa Cruz、Zorlacのアートワークで、VCJ、ジム・フィリップス、パスヘッドのイラストはグラフィックデザイン寄りだったVisionやSimsのものよりずっと魅力的だった。
V: '80年代後期にPowell Peraltaに入ったとき、VCJのグラフィックを受け継ぐことにプレッシャーは感じた?
S: めちゃくちゃ怖かったよ(笑)。1988年10月にジョージ・パウエルとの面接のために飛行機で呼ばれたとき、そのあとVCJと一緒に夕食に行ったんだ。そこで彼は「ちょっと休みが必要なんだ。長期休暇を取ろうと思ってる」と話していてね。だからいざ採用が決まって1989年1月にPowell Peraltaで働き始めたとき、アート部門に入ったらVCJのオフィスが丸ごと消えていたのを見て本当に衝撃を受けた。そこには空っぽの作業スペースが残っているだけ。自分はてっきり彼の下で、アシスタントのような形で働くものだと思っていたから、いきなりあの伝説的なポジションを引き継ぐなんて思ってもいなかった。だからもう頭の上に巨大な重しが乗っかったような気分だったよ。だって「Powell Peraltaのグラフィックを台無しにしたヤツ」として歴史に名を残すなんて絶対イヤだったから。まあ、今でもそう思ってる人がいるかもしれないけどね(笑)。
V: レイ・バービーとスティーブ・サイズのプロモデルを担当したときはどんな感じだった?
S: 両方ともいわば白紙の状態、つまり以前にVCJのグラフィックが存在しなかったことは本当に救いだった。特にレイは、あの独特にユルいスタイルを持っていたうえに、すでにラグドールの基本アイデアまで用意してくれていたのが大きかった。幸運だったのは、当時はまだグラフィックの入れ替わりが今ほど速くなかったこと。だからじっくり時間をかけてグラフィックに取り組んで、たくさん失敗して学び、最終的なイラストに落とし込む前にしっかりコンセプトを練り上げることができたんだ。

V: '90年代に突入してシーンは大きな変革を迎えたよね。PowellからWorld Industriesへ移る際はどうだったの?
S: 正直、PowellからWorldへの移行はまったくスムースじゃなかった。Powellでの最後の1年は本当にフラストレーションだらけで、自分はまだ現役でストリートに出ていて、シーンがどう変わっていっているかを肌で感じていた。World、Blind、101、H-Street、New Deal、Real、その他の小さくて機動力のあるスケーター運営のブランドたちと比べて、Powellは完全に時代遅れに見え始めていたんだ。そんな状況だから、自分は会社のなかで厄介者みたいになっていた。ジョージとはグラフィックの方向性についてよく言い合いになったし、フランキー・ヒルの”Clint Eastwood”のグラフィックのときなんて訴訟沙汰になると思ったらしくて本気で怒鳴られたことさえある。そんななか、1991年11月に大規模なレイオフがあって、ジョージは自分を切ったんだ。予兆はあったはずなのに、実際に言われたときは完全に不意打ちで打ちのめされたよ。ウィスコンシンに戻って失敗者として人生をやり直すしかないのかと思った。でも幸運なことに、その翌週にスティーブ・ロッコが自分がクビになったと聞きつけて電話をくれた。「World Industriesで働かないか?」って。自分はもともとWorldのすべて、つまり広告、グラフィック、ビデオが大好きだったから、即答で「やる」と言ったよ。Powellは9時から5時までのフォーマルな会社で、出退勤をきっちり記録するような環境だった。でもWorldは真逆。構造なんて存在しない、完全なるカオス。いつ何が起きてもおかしくないし、それが最高に楽しかった。好きなときに働けるし、好きなときにスケートに行ける。ロッコなんて、出社してきて「今日、海の波がいいぞ」と言い出して、みんなでボートに乗ったりジェットスキーしに行ったりしていたくらい。そんな自由さが、逆に自分をもっと働かせた。もっとやりたい、もっと描きたいって思わせたんだ。週末という概念は消え去って、マーク・マッキーと自分は毎日のように12時間以上働いていた。互いに刺激し合って、より良いグラフィックを作ろうとして、エネルギーをぶつけ合っていたんだ。
V: World Industries時代は「アナーキーと革新」とよく形容されるけど、ロッコの下で働く環境はどんな感じだった?
S: Worldに入った当初、ロッコは「最高のボードグラフィックが欲しい。必要なものにはいくらでも払う」とはっきり示していた。だからこそクリエイティブな解放感が本当に中毒になるほどだった。とにかくロッコを興奮させたい一心だったんだ。彼は大人だけど大人じゃない。大きな子どものような存在で、とにかく面白いもの、ヤバいものを作りたかった。Powellでは制作カレンダーやマーケティングのスケジュールがすべてで、新商品が出るまでに数ヵ月かかるのが当たり前だった。でもWorldでは、ロッコが「これやろう」と言ったら、そのグラフィックのデッキがわずか2週間後には店頭に並ぶなんてことも普通にあった。そんなスピード感と勢いに満ちた環境で働けるのは本当に刺激的だった。
V: 当時のグラフィックは挑発的で、ときに不快で、そして爆笑するようなものでもあったよね。あのような表現は、意図的にユーモアやタブーの境界を押し広げていたのか、それとも時代の空気が自然とそうさせていたのか。どっちだと思う?
S: 当時の自分たちは、ただ その瞬間を生きていただけだったと思う。'80年代のブームが完全に終わって、スケートは人気を失い、業界そのものがひっくり返っていた。自分たちがやっていたことの多くは、単純に「自分たちが笑えるかどうか」だけで決まっていたんだ。当時はショッキングなものほど面白かったし、「どこまでやったら怒られるか」ということを試す感覚があった。しかもWorldでは相当なところまで行けてしまった。ロッコがこの世で一番嫌うのは、「それはダメ」と誰かに言われることだったから。自分たちはそのエネルギーを糧にして動いていたんだ。Big Brotherが生まれたのも、まさにその延長線上。TransWorld SKATEboardingがロッコの広告掲載を断ったことで、彼は「ふざけんな、だったら自分で作るわ」とキレて、自分がやりたいことを何でもできる雑誌を立ち上げたんだよ。

V: Rocco時代で一番カオスだった出来事は?
S: おそらく一番クレイジーだったのは、ロッコがBig BrotherでTransWorldの「Pro Spotlight」 をパロディにした「Ho Spotlight」をやりたいと言い出した日のことだね。ストリッパーにインタビューする企画で、本当に何人か呼んじゃったんだよ。その日の午後に彼女たちはロドニー・マレンのオフィスのど真ん中でストリッパーとしてのお仕事を披露し始めて、部屋の周りには当時の未成年のプロ/アマのスケーターたちがズラッと並んで見ていた。UPSの配達員までその場に居合わせて、普通に観ていたからね。ショーが終わったあと、ロッコとロドニーが彼女たちにインタビューしようとしたんだけど、たいして面白いことも言わず、結局その記事はボツになった。さらに問題だったのは、ストリッパーたちと一緒に写っている写真が撮られたこと。スケーターたちは「親にバレたらヤバい!」と完全にパニックになって、Big Brotherのオフィスから35mmスライドを全部盗んでいったんだよ(笑)。
V: 振り返ってみて、'90年代のボードグラフィックを特別なものにした要素は何だったと思う?
S: 本当に全部。ただ当時のスケートインダストリーはかなり小さくて結束も強く、メインストリームの目にはまったく触れない世界だったんだ。さらに言えば、ロッコがグラフィックの基準を途方もなく高いところに設定してしまったから、どのブランドもそれに応えようとそれぞれのやり方で攻めたグラフィックを作っていた。でも'90年代後半になってスケートの人気が再び高まってくると、かつてのようなぶっ飛んだグラフィックでは通用しない場面も出てきた。親が子どものためにデッキを買うようになって、ショップで攻めたグラフィックを目にすると店に文句を言ってトラブルになることがよくあったんだ。その結果、ショップ側がどのグラフィックなら仕入れることができるか強くコントロールするようになって、最終的にボードグラフィック史上もっとも最悪のものが生まれてしまった。ロゴだけのデッキのことだよ。
V: '90年代を象徴するグラフィックを1〜2枚挙げるとしたら?
S: 自分が選ぶとしたら、Blindのジェイソン・リーの“American Icons”と、Realのジム・シーボーの“Hanging Klansman”。あのあたりから風刺や社会的メッセージがボードグラフィックに入り込み、単なるドクロやドラゴンのようなおふざけモチーフを超えた表現へと進化し始めたんだ。当時としてはまったく新しい発想で、ボードグラフィックのアプローチを一気に塗り替えた。それが今でもあの時代の特定のグラフィックが強烈に記憶に残り続けている理由だと思う。

V: StrangeLove Skateboardsを立ち上げた理由には、アーティストが搾取されているという思いもあったのかな?
S: ある意味ではその通り。というのも自分は数年間フリーランスとして働いていたんだけど、多くのブランドがグラフィックに対して本当にわずかな報酬しか払わない現状にずっと悩まされていたんだ。同時に他のアーティスト仲間からも、報酬が安すぎたり、ブランドがなかなか支払いしなかったりと、同じような恐ろしい話を聞いていた。その一方で、自分が25年以上前に描いたグラフィックがいまだに復刻され続けているのに、そこから1セントすら受け取っていない。状況はどんどん悪化して、「このままアーティストとして食べていけるんだろうか」と不安でパニック発作を起こすほどになって、仲間の会社の出荷部門に雇ってもらえないか相談しようかと本気で考えていたほど。そんなとき幸運だったのは、ニック・ハルキアスという仲間の存在だった。彼も自分と同じくあの時代のボードグラフィックが好きで、自分たちはその無礼で遠慮のない精神を軸にしつつ、同時にアーティスト仲間をもっと敬意を持って扱うブランドをつくろうと決めたんだ。もし彼らのグラフィックがヒットしたら、追加生産ごとにちゃんと追加の報酬を払う。そして自分たちがそのグラフィックを使ったデッキの生産を終えた後は、作品の権利をアーティスト本人に戻す。理想主義的かもしれないけれど、自分たちには資金を援助してくれる出資者なんて誰もいなかった。ただ自分とニック、1枚のクレジットカード、それからずっと「いつかやりたい」と思っていた山ほどのアイデアがあっただけ。そして止める人が誰もいなかっただけ。

V: StrangeLoveのビジュアルアイデンティティは、遊び心があって、反骨的で、どこかすごく個人的な雰囲気があるよね。そのエネルギーを保ちながら、どうやってビジネスとして成立させているの?
S: 正直に言うと、ここ数年のスケートインダストリーのどん底状態を経て、そのエネルギーを保つのはどんどん難しくなっているね。コロナ明けの浮かれムードの反動で、ショップからブランド、メーカーに至るまで、業界全体がかなり混乱してしまった。とにかくみんな大変な状況なんだ。幸い自分らはかなり小さなブランドでほぼ従業員もいないような規模だから、市場の変化にすばやく対応できている。でも一番自分を苦しめているのは自分自身なんだよね。というのも自分はただ何でもいいからスケートボードの裏にプリントすることはしたくないんだ。カタログの穴埋めみたいなグラフィックなんて作る意味がないし、カルチャーにとって何のプラスにもならない。ただ同時に、「アート系のブランド」として見られたくもなかった。壁掛け用にしか買われないブランドだと思われることほど、フラストレーションの溜まることはないから。そのイメージを払拭するのに本当に苦労した。とはいえ、それが完全に自分たちのせいというわけでもない。ロゴデッキ以外で言えば、業界が犯してきた最悪の過ちのひとつは、企業が意図的にデッキ、特にスクリーンプリントデッキを限定商品として打ち出し、コレクター心理を煽って転売ヤーに迎合してきたことだと思う。それによって、スケートボード本来の意味が歪められてしまった。そして今、そのツケを払っている、あるいはこれから払うことになる会社やコレクターが確実に出てきているはずだよ。


V: 今スケートショップのボードウォールを見てボードグラフィックの現状をどう感じる? 最近のグラフィックは安全すぎると思う? それとも単に変わっただけ?
S: スケートボードというカルチャーは、つねに進化し続ける「未完成のプロセス」みたいなもので、グラフィックも同じ。30年以上前の「あの時代」を知らない若い世代にとっては、今の状況こそが彼らのリアルで、彼らが知っている世界であり、彼らがつくっているものなんだよ。自分の好みとは違うかもしれないけれど、そもそも自分のような中年向けにつくられているわけじゃないんだよね。とはいえ、ショップのボードウォールを見ると、ブランドごとの違いが分かりづらくなっていることには少し寂しさを感じる。どのブランドも似たようなグラフィックが多くなって、特定のトレンドやルックスが流行ると、みんな同じ方向に寄っていってしまう。その結果、ブランドの個性が埋もれてしまうんだ。特にブティック系のショップでは、壁一面がほぼ同じブランドのデッキに見えてしまうことすらある。確かに「これはすごい」と思わせるグラフィックに出会う頻度は少なくなったかもしれない。でもそれは自分が完全に別の時代の感性に染まっているからというのも大きい。今でも本当に素晴らしい作品は必ずある。ただその「宝石」にたどり着くには、昔よりもはるかに多くの「消耗品的なグラフィック」の山を掘り起こす必要がある。そんな感じかな。
V: '90年代にショーンが持っていたような自由奔放なクリエイティビティは、SNS全盛でブランディングも厳しくなった今の時代でも成立すると思う?
S: いや、正直いって無理だろうね。今は世間の目から逃れること自体がほとんど不可能だし、Big Brotherのような雑誌だってもう成立しない。それに人は風刺や皮肉を読み取る力を失ってしまった気がする。画像の文脈や意図を理解できないことが多い。だからといって、まったく何もできないわけではない。自分たちはそのために、SNSを完全に避ける形でStrangeLoveというシークレットクラブを作ったんだから。
V: ボードグラフィックでキャリアを築きたい若いアーティストにアドバイスをするとしたら?
S: 自分を安売りしないこと。みんな自分のアートがスケートボードの裏に載るのを見たい気持ちはよく分かる。でもちゃんとしたキャリアを築きたいのなら、ほとんど無償に近い仕事や友達感覚の握手だけで受けるような仕事から始めてしまうと、ブランドはキミをリスペクトしないし、結果的に他のアーティストたちにも悪影響が出てしまう。それから作品がどのように、どれくらいの期間使われるのかを明記した契約を必ず用意すること。使用権をすべて渡してしまうのか? ある日おもちゃ屋に行って、自分のアートがフィンガーボードとして勝手にライセンスされていたらどうするのか? 「プロとして扱われたい」と思うことは何も悪いことじゃない。たとえ業界がどれだけ「プロらしくない」と知られていたとしてもね。
V: 一言で答えて。ショーンにとってスケートボードとは何か、そして今のショーンにとってグラフィックアートとは何か?
S: ちょっとクサい言い方に聞こえるかもしれないけど、自分にとってスケートボードとは新しいトリックをメイクすること、あるいはこれまで誰もやったことがないことを成し遂げることなんだ。たぶん今の自分がボードグラフィックに向き合う姿勢も変わらず同じで、NBDを出せる可能性があると思うだけでワクワクする。ごめん。長くなったけど、そもそも自分は一言で答えられるようなタイプじゃないんだ。strangeloveskateboards.com のブログを見ればわかるよ(笑)。
Sean Cliver
@seancliver
Powell Peraltaでキャリアをスタートし、その後World Industriesでブランドのビジュアルアイデンティティを形作ったアーティスト。スケート史上もっとも影響力があり、ときに物議を醸した多くのグラフィックを生み出してきた。現在StrangeLove Skateboardsを運営し、独自の作品世界を発信し続けている。